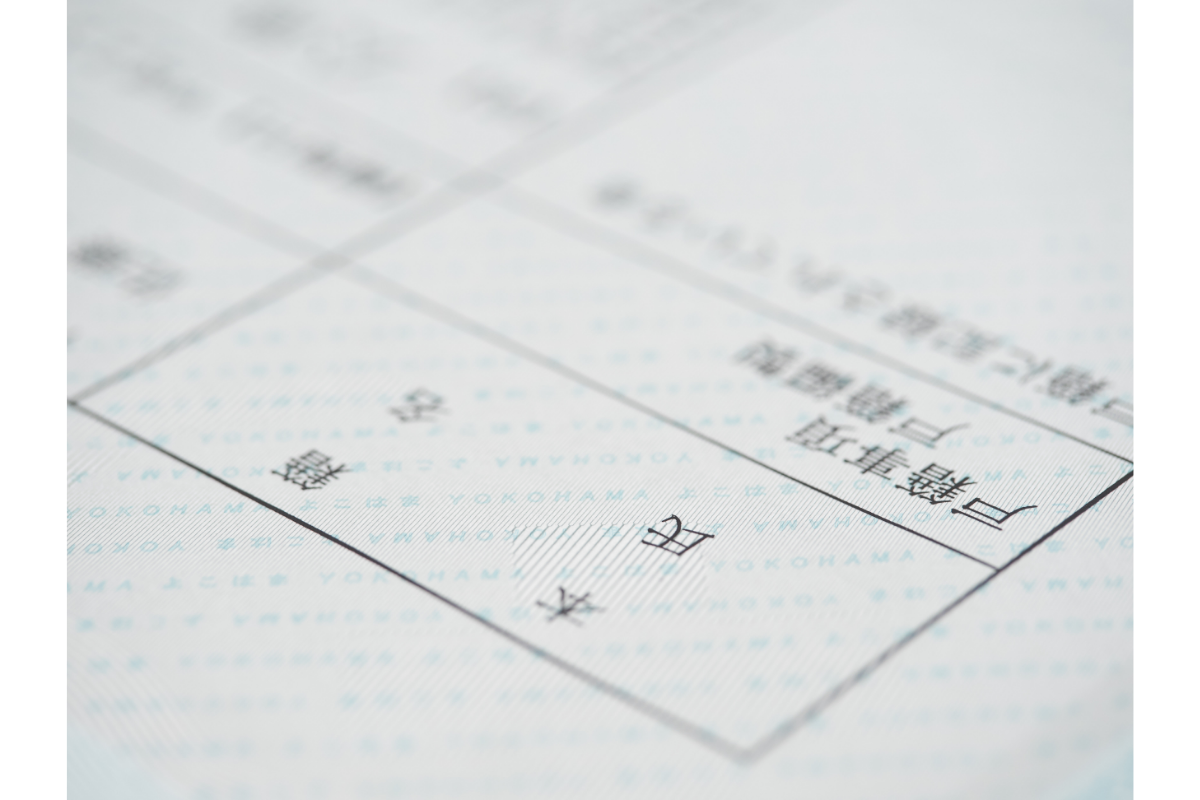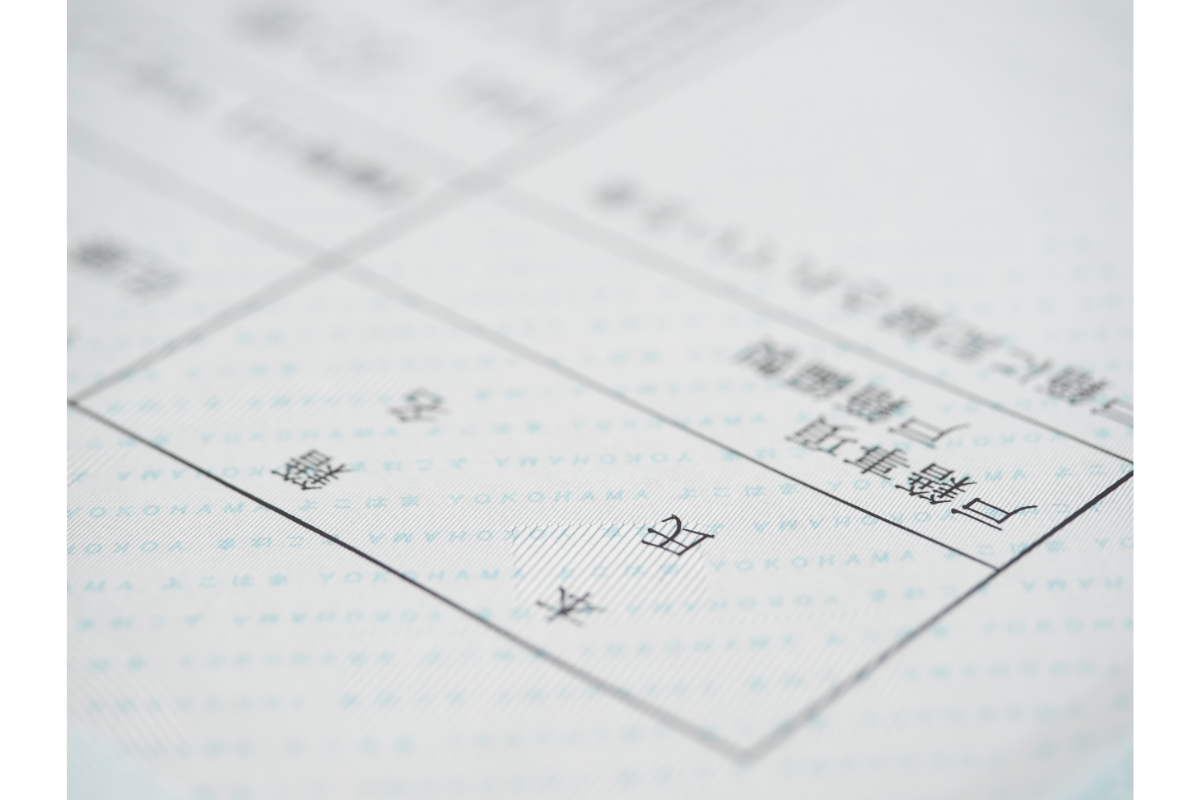3月 06日, 2025年
マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニで戸籍謄本や戸籍抄本が取得可能になっていることをご存じですか?
2月 10日, 2025年
2026年2月2日より「所有不動産記録証明制度」が開始される予定です。の制度により、特定の名義人が全国に保有している不動産の一覧が記載されている「所有不動産記録証明書」の発行をしてもらえるようになります。
2月 03日, 2025年
遺産分割協議がもめているなど、3年の期間内に相続登記の申請義務を履行することが難しい場合に利用できる、相続人申告制度、ご存じですか。相続登記が義務化されたことに伴い導入された制度です。
10月 30日, 2024年
不動産の共有でトラブルを抱えていませんか?当事務所では、このたび「共有解消サポート」のページを新設いたしました。
2月 20日, 2024年
電動キックボードの逆走について正しく理解していますか?もちろん電動キックボードでも逆走は基本的には道交法違反であり、許されていません。
10月 04日, 2022年
遺言で会社に対する株式、不動産などの遺贈をする場合には、意外な税金の負担が発生することがあるため、注意が必要です。